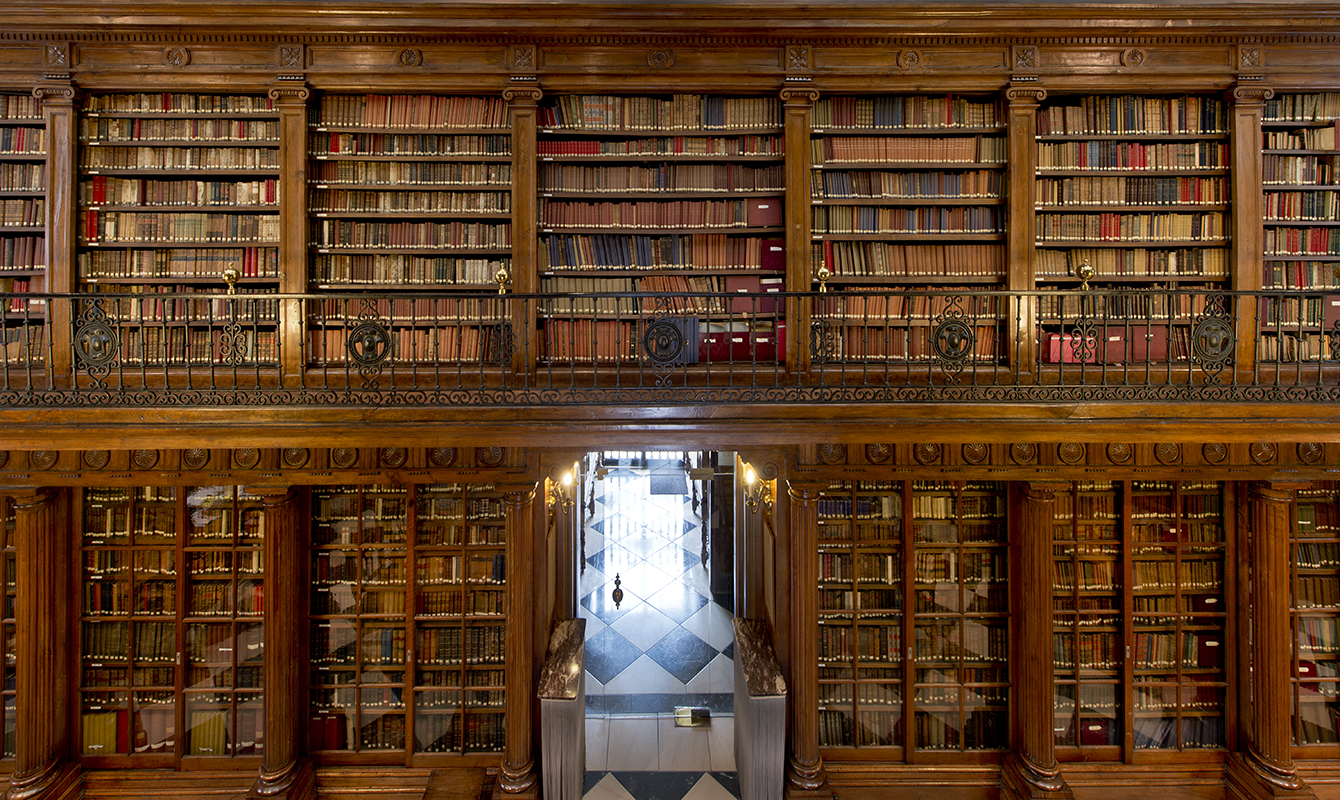情報設計についてもっと詳しく
Webサイトの情報設計の守備範囲は多岐にわたり、つかみどころない特徴もあります。
- 見つけやすさ、理解しやすさといったユーザビリティ
- ツリー型やファセット型など、情報体系と構造
- 分類やラベリングなど、情報の整理
- 行動文脈に則したナビゲーション
- 言語と意味と関連性
など、相互に関係しながら全体を構成するという厄介な分野でもあります。
これまでにも、なるべく具体的に詳しく解説した記事がありますので、是非ご参照ください。
- Webデザインと「ケチャップ問題」
ユーザーの行動文脈と情報の分類方法に関する解説。
- 「製品の情報」とは?キチンと設計するために定義してみた(前編)
「情報」が持っている属性や付帯情報をどのように捉えたら良いか?を解説。
- UXの事件は現場で起きている〜令和元年のかき揚げ事件〜
ユーザーのメンタルモデルとのミスマッチを具体的な事件で解説。
- 「ムスロ丼」とカスタマージャーニーマップ
検索行為と語彙の問題を中華料理の例で解説。
- コーポレートサイトのWebコミュニケーション設計に最強?のフレームワーク「TCFRO」
ユーザーの視点で設計を行う簡単なフレームワークを解説。
情報設計は専門家に相談しましょう
情報設計について理解が進むと、より一層むずかしさを実感してくると思います。実際にはたくさんの経験値をためないと設計は上手になりません。現実的には社内で豊富な経験を詰むことは困難でしょう。(何度もリニューアルを経験することは稀です)
まず、自社内でできることとして、社内の事情やお客様の具体的なニーズ・行動文脈などを汲みあげることです。そして自社内できちんとそれ検討して、専門家に向けて正しい情報をアウトプットすることです。そこに尽力しましょう。
分類や整理・構造化をするプロセスに入ったら専門家の客観的な視点を頼りにしましょう。

専門家に自社の情報をきちんと伝えることができれば、ユーザーにもきちんと「伝わる」コミュニケーションが成立するようになるはずです。